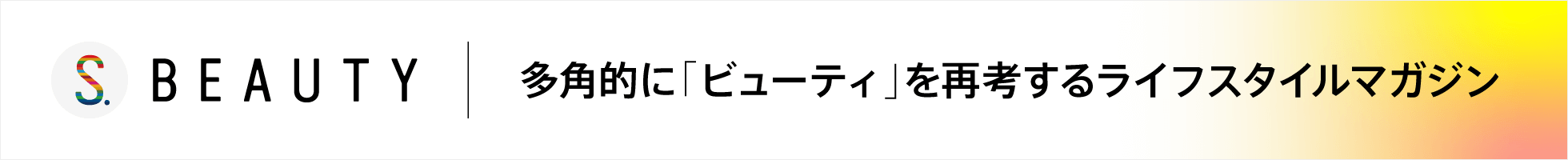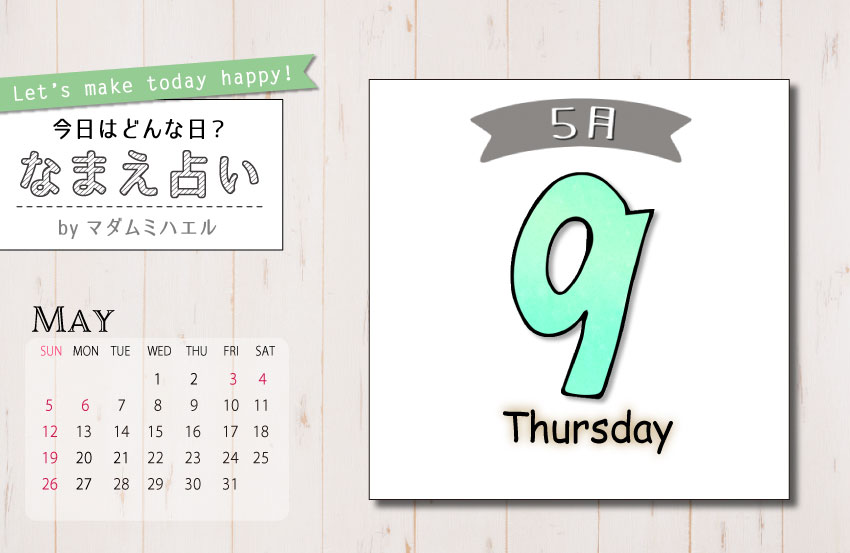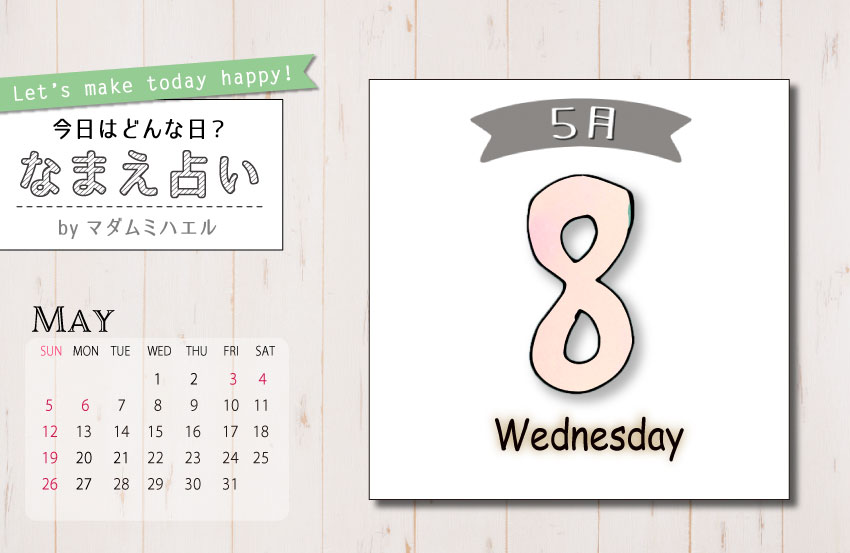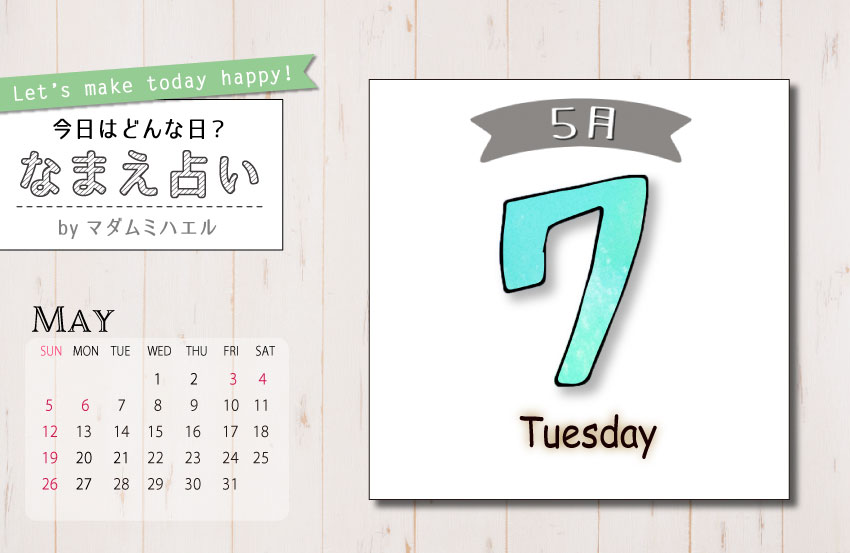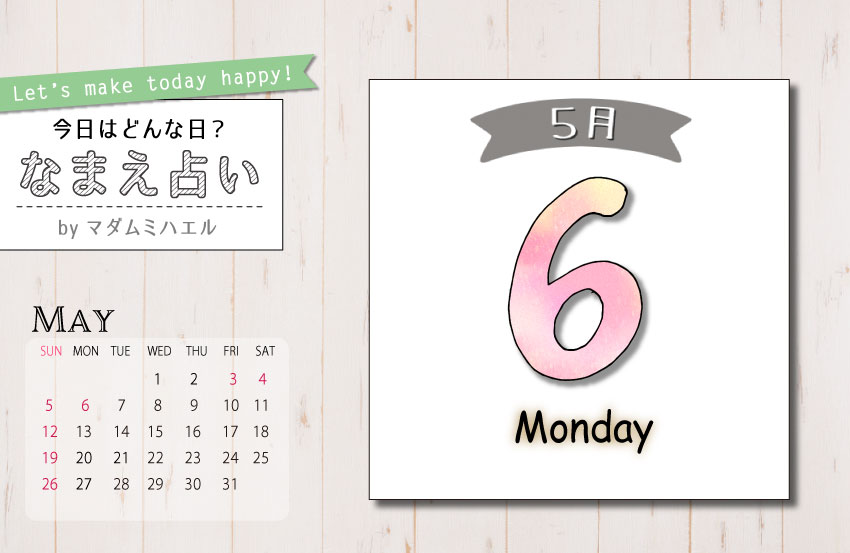「トイチ」――。
“10日で1割の利息”という意味からこう呼ばれることはご存知の人も多いだろう。『ナニワ金融道』や『難波金融伝ミナミの帝王』、『闇金ウシジマくん』など今まで数多く漫画にもなってきた題材でもある。利息制限法や出資法の年利を超えるため、法律違反の「闇金」だが、キャッシングで返せなくなった人が足を運び、そのまま抜け出せなくなって身体を売ったという噂話も多く聞く。しかし、実際にトイチと関わったことがある人はどれだけいるだろうか。
しかし、私は今から約20年前、「トイチ」だったであろう事務所のドアを叩いた経験がある。大手出版社数社でライターとして働き、当時20代にして年収800万近くあったにも関わらず、借金まみれだった。
もう人生は終わりと思ったが、今は借金がなく、堅実な生活を送れている。そこにはある「意外な恩人」の存在があった。そのいきさつと顛末をお話しよう。
複数の大手出版社で多くの人気雑誌に携わってきた売れっ子ライターも、実は20年ほど前、借金地獄にはまり、「人生はもう終わりだ」と思ったという。
1カ月40~50万円の支払いと返済
今から20年ちょっと前。世の中はバブルが崩壊し、冷え込んでいたが、バブル崩壊後も出版業界は比較的景気がよかった。雑誌文化が花開いた時代でもあり、次々と新雑誌が生まれていった。当時、20代後半だった私は、女性誌を中心にライターやフリーの編集者として仕事をしていた。抱えていた媒体数は、6~7誌。年収は800万は下らなかった。
ところが、当時私は最も多い時で500万近い借金を背負っていた。同世代の女性よりも多い年収がありながらも、毎月火の車。消費者金融のA社毎月3万円、P社に3万円、T社に2万円。クレジットカードのキャッシングで借りた返済が、Mカードで約3万円、S社で4万円、O社5万円、I社で5万円……。今思い出しても恥ずかしく、冷や汗が脇の下ににじむ。とにかく、ありとあらゆるところに借金をしまくり、ショッピングなどのカード支払いも加えたら、毎月40~50万近く返済する生活になっていた。
仕事が次々なくなり、パートナーも無職に
収入があったにもかかわらず、なぜこんなにも借金がかさんでしまったのか……。それには大きく2つの理由があった。
ひとつは、景気がいいといいながらもフリーランス稼業は水商売であることが影響していた。20代半ば、バブル崩壊直後に、メインでやっていた雑誌媒体がまず休刊になった。フリーランスはレギュラーで仕事を持っていても、雑誌が休刊になれば、その出版社からの収入は当然なくなってしまう。なんの保証もない。中には次の仕事を紹介してくれる媒体もあったが、そこはスタッフ数も多く、さらに私は他の出版社の仕事も受けていたため、「どうにかなるから大丈夫」と見栄を切ってしまったのだ。
ところが、蓋を開くと、他の出版社もバブル崩壊の痛手を受けて、雑誌が休刊。その当時抱えていた仕事を一気に3誌も失ってしまうことになった。とはいえ、もともと楽観的な性格だったので、「大丈夫、仕事に困ったことはないし」と最初は正直タカをくくっていた。しかし、1カ月、2カ月……と収入がなくなれば当然、貯金は減ってくる。当時20代半ば、バブルを経験し派手にお金を使うことに慣れていた私は、当然貯金額も低かった。困ったときに、と貯めておいた180万円はあっという間に激減していった。
さらに、最悪なことに当時、いっしょに暮していたパートナーがうつ病で仕事をやめてしまったのだ。広告制作会社で働いていたのだが、バブル崩壊後の仕事は日ごとに目減りしていった。ある日彼は駅でパニック障害を起こし、そこから会社に行けなくなり、無職に。もともと我が家に居候で転がり込んでおり、貯金もほとんどない状態。2週間に1度の病院以外は、午後まで寝て、好きなゲームや小説を読んで過ごす日々が始まったのだ。
病気が落ち着けば、きっと仕事をするだろう、と思っていたのだが、その後別れるまでの5年間、彼は仕事をせず、高等遊民のように好きなことだけして暮らした。
すべては自業自得だ。フリーランスという浮き沈みが激しい仕事を選びながらも、貯蓄せず、好き勝手に生きていれば当然、お金は底をつく。しかし当時、花形の雑誌で仕事をしていた私は、お金がない素振りなど見せられない。財布に万札など一枚も入っていないにもかかわらず、伊勢丹でブランドものを買い、仕事仲間と人気のレストランにいつもと同じ顔で食事に出かけた。